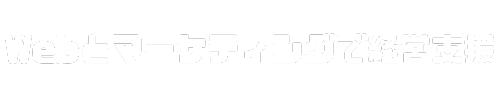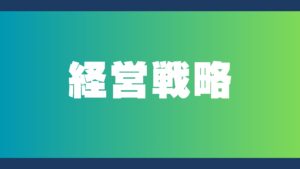中小製造業にとって「損益分岐点分析」は、生き残りと成長を左右する重要な指標です。
売上はあるのに利益が出ない、価格転嫁ができない、原価管理が曖昧…。
そんな課題を抱える経営者が、数字に基づいた価格設定と利益計画を実現するための考え方と実践方法を解説します。
本記事のポイント
- 損益分岐点で利益の見える化が可能
- 固定費・変動費を分解し利益計画を作成
- 価格設定や投資判断の武器になる
なぜ「損益分岐点分析」が必要なのか?
-150x150.jpg)
損益分岐点を理解していないと、経営判断は勘と経験に頼りがちです。本章では「なぜ必要か」を明らかにし、管理会計の重要性を提示します。
(1)利益が見えない経営の怖さ
ある中小製造業の経営者は、決算書を税理士に任せきりで「今月いくら売れば利益が出るのか?」をあまり把握していませんでした。
売上はあるのに、資材価格や人件費の上昇で利益が出ない…。
まさに「どこまで売ればいいのか分からない経営」です。
これでは適切な価格設定も難しく、赤字経営から抜け出せません。
(2)コストの正体をつかむ
コストには「変動費(材料費・外注費など生産量に比例する費用)」と「固定費(人件費・家賃・減価償却費など売上に関係なく発生する費用)」があります。
どのコストを削るべきか分からないままでは、闇雲なコスト削減になり、強みである技術力まで失われるリスクがあります。
損益分岐点分析は、この「どのコストに手をつけるか」を明確にしてくれるのです。
(3)制度会計ではなく「管理会計」へ
決算書は金融機関や税務署のための「制度会計」です。
しかし、経営者が日々意思決定するために必要なのは「管理会計」です。
損益分岐点分析はまさにその第一歩であり、「いくら売れば損益トントンになるか?」「年間目標利益が3,000万円の為の売上高・費用は?」を見える化してくれます。
損益分岐点を計算する方法
-150x150.jpg)
損益分岐点分析を行うには、原価管理と固定費・変動費の分解が必須です。本章では計算方法と利益を上乗せしたシミュレーションを解説します。
(1) 原価管理のスタートライン
まずは「原価管理」を行うことが前提です。
1つの部品を作るのに材料費はいくらかかるのか、加工時間と人件費はどの程度か。
ここを把握しなければ、正しい損益分岐点は算出できません。
ある中小製造業は「なんとなく」で原価を見積もっていましたが、この精緻化こそ経営改善の土台となります。
(2)固定費と変動費の分解(固変分解)
損益分岐点を求めるには、費用を固定費と変動費に分ける必要があります。
例えば、年間の人件費3,000万円は固定費、材料費率40%は変動費といった具合です。
売上高 - 変動費 - 固定費 = 0(利益)
⇒ 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1-変動費率)
という形で算出でき、「何円売れば黒字になるか?」を明確にできます。
(3)利益を乗せたシミュレーション
単に「赤字を出さない」だけではなく、目標利益を上乗せした計算が重要です。
例えば「年間1,000万円の利益を出したい」と設定すれば、損益分岐点売上高にその分を加えて逆算できます。
これにより「目標売上」「必要な価格転嫁」「受注単価の見直し」が具体化されます。
損益分岐点をどう活用するか?
-150x150.jpg)
分析結果を活かすことで、利益計画・価格転嫁・投資判断が数字で裏付けられます。本章ではその具体的な活用法を見ていきます。
(1)利益計画の羅針盤に
損益分岐点は「今後どれだけ売上を伸ばせばよいか」「コストをどの程度抑える必要があるか」を教えてくれます。
例えば「月商2,500万円で利益ゼロ」と分かれば、2,800万円の売上増加を狙うのか、2,500万円でも利益が残るようにコスト構造を変えるのか、判断基準が得られます。
(2)適切な価格設定と価格転嫁
資材価格が高騰している今こそ「価格転嫁」が不可欠です。
損益分岐点を理解していれば、「これ以上下げると赤字になる」という最低価格を把握できます。
逆に「この強みの部品は高付加価値だから適正に上乗せできる」という判断にもつながります。
価格交渉は感覚ではなく、数字で裏打ちされてこそ通用します。
(3)投資判断を支える
損益分岐点分析は「攻めの経営」にも役立ちます。
例えば新しい設備投資や賃上げを検討する際、「固定費が増えると損益分岐点はいくら上がるのか?」を事前にシミュレーションできます。
これにより「リスクを踏まえた前向きな投資判断」が可能になるのです。
また外部に依頼した方がコストを下げられるなら外注依頼するか検討材料になります。
数字で現状把握し、強みを活かす経営へ
損益分岐点分析は単なる数字遊びではなく、「経営の見える化」の第一歩です。
利益を確保する最低ラインを知ることで、価格設定や投資判断に自信を持てるようになります。
ただし忘れてはいけないのは「強み」を活かすことです。
精緻な部品設計・生産力という強みを守りながら、価格転嫁や原価管理で利益体質に変える。
そのための道具が損益分岐点分析なのです。