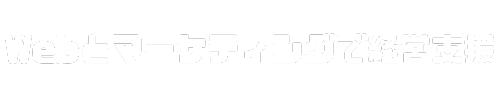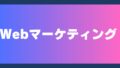美味しい野菜を真面目に作っていても、思ったように利益が残らない…。
そんな農家の方にこそ知っていただきたいのが「顧客の顧客」という視点です。
JAや直売所の“その先”にいる消費者の困りごとを想像し、そこに応えることで、価格競争に巻き込まれない強い農業経営が可能になります。
本記事のポイント
- 顧客の先を知ると、売れる形が見える
- 自分でもできる3つの情報収集法
- “選ばれる”農家になった具体事例紹介
「作って終わり」では、もう稼げにくい時代
-150x150.jpg)
「作って終わり」の時代は終わりつつあります。今求められるのは、「誰が、なぜ、その野菜を選ぶのか?」までを考えた農業です。“売れる農業”へ第一歩を踏み出しましょう。
(1)なぜ同じ品質の野菜でも、儲かる農家と儲からない農家がいるのか?
真面目に手間ひまかけて育てた野菜でも、思ったように利益が残らない。
そんな悩みを持つ農家の方にお会いしました。
なぜ同じように作っているのに、儲かる農家と儲からない農家がいるのでしょうか。
実はその差は、「売り先の先まで考えているかどうか」にあります。
JAや集荷業者に卸して終わり、直売所に出して終わりでは、「誰のために何を作っているのか」が見えにくくなります。
一方、儲かっている農家は「自分の野菜が、誰に、どんな場面で、何のために使われているか」を意識しています。
その“先”にいるのが「顧客の顧客」です。
(2)「顧客の顧客」って何?農家に関係あるの?
農業で「顧客の顧客」と言っても、ピンとこないかもしれません。
でも、たとえばJAにトマトを出荷しているなら、そのトマトはどこへ行くでしょう?
スーパー?飲食店?介護施設?
そのさらに先には「家庭の食卓」「親子のお弁当」「健康に気を遣う高齢者の毎日の食事」があります。
その“先”のことを考えると、作り方や品種、サイズ、梱包、収穫タイミングなど、見直すポイントが浮かんできます。
たとえばトマト農家であれば、以下のようなケースが考えられます。
- スーパーでは「パック詰めで日持ちするトマト」が求められている
- 飲食店では「皮がむきやすく、調理しやすいトマト」が好まれる
- 高齢者施設では「酸味が少なく、食べやすいサイズ」が支持されている
こういった情報を把握することで、自分の農業を“売れるかたち”に変えるヒントが得られるのです。
(3)「美味しい」だけじゃない。困りごとを解決する野菜が、選ばれる理由
もちろん、農家として「美味しい野菜をつくる」は大前提であり、とても大切なことです。
ただ、それだけでは競合との差別化にはなりづらい時代です。
どの農家も美味しい野菜を追求しているからこそ、「その美味しさが、誰の、どんな困りごとを解決するのか?」まで踏み込むことが差になるのです。
- 共働き家庭には、「洗ってそのまま食べられるミニトマト」が便利。
- 高齢者家庭には、「柔らかく皮が薄いトマト」が食べやすい。
- 飲食店には、「サイズが揃ったトマト」の方が盛り付けや仕込みがしやすい。
「美味しさ」+「便利さ」「扱いやすさ」「ストーリー性」があることで、価格競争に巻き込まれずに“選ばれる”ようになります。
「顧客の顧客」をどう調べる?農家でもできる3つの方法
-150x150.jpg)
「顧客の顧客」は遠い存在に感じるかもしれませんが、ちょっとした工夫と行動で、ヒントはたくさん集まります。農家でもできる具体的な3つの方法をご紹介します。
(1)JA職員・バイヤー・販売員に一言聞いてみる
JAや市場、スーパー、直売所など、販売の中間にいる人に「誰に売れてるのか?」「どんな場面で食べられているか?」と聞くだけで、有益なヒントが得られます。
たとえば、「最近は家庭よりも業務用需要が増えてるよ」と言われたら、飲食店向けの提案を考えてみるチャンスです。
誰もが忙しいなか、ちょっとした質問が「考えるきっかけ」になります。
(2)直売所やマルシェで「買ってくれる人」と会話する
直売所で接客したり、週末マルシェに立つことで、「実際の購入者」と顔を合わせることができます。
「小分けされていると嬉しい」「冷蔵庫に入りやすいサイズがいい」「家族の好みに合わせてる」など、生の声は商品開発のヒントの宝庫です。
顧客の行動を観察するだけでも「ニーズ」が見えてきます。
(3)仲間や専門家と対話して“仮説”をつくる
すべてを自分ひとりで考えなくてもいいのです。
商工会議所の支援員や、農業経営アドバイザー、販路拡大の専門家、異業種の仲間と話すことで、「あ、それならこういう売り方があるかも」と視点が広がります。
たとえば、あなたのトマトを「ジュース原料」に使いたい飲食店とつながることもあり得ます。
仮説→行動→検証を繰り返すことが、農家にも大切なマーケティングの考え方です。
「顧客の顧客」を意識した農業経営の成功事例
-150x150.jpg)
実際に「顧客の顧客」を意識することで成果を出した農家の事例をご紹介します。あなたの農業経営にもきっと活かせるヒントがあります。
(1)「見た目の悪いトマト」が飲食店で大人気に
あるトマト農家は、B級品のトマトを「もったいない」と思っていました。
しかし、飲食店のシェフと話してみると、「ソースやピューレに使うから、見た目は関係ない。
むしろ味が濃いほうが嬉しい」との声。
そこで、“加工用トマト”として新たな販売ルートを開拓。
価格は安くても、廃棄ロスが減り、利益はしっかり確保できました。
(2)スーパーの「日持ちするトマトがほしい」の声で品種変更
別の農家では、「1週間は棚に並べたい」というスーパー側の要望をきっかけに、より日持ちする品種に切り替えました。
単価はやや下がったものの、廃棄が激減し「安定供給してくれる農家」として評価が向上。
固定取引になり、年間売上はむしろ増えました。
(3)子育て世代の「めんどう」を解決する加工セットで新販路開拓
とある農家は、マルシェで「子どもが野菜を食べてくれない」「切るのが面倒」という声を聞き、カット済み野菜+簡単レシピ付きのセットを開発。
これがSNSで話題になり、通販の受注が急増。
家族構成や生活背景まで考えた商品づくりが、大きな成果につながりました。
「売れる農業」は“その先の顧客”から始まる
これからの農業は「美味しさ+課題解決力」が鍵になります。
顧客のさらに先にいる人の声に耳を傾けることで、あなたの野菜はもっと選ばれる存在になります。
大きな改革は不要です。 小さな気づきと行動の積み重ねが、農業を安定した「続けられる仕事」へと変えていきます。