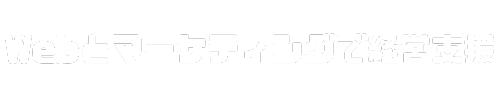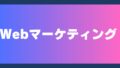上越妙高の農業組合で農作業のお手伝いをさせていただき、現在18名の地域農家の方から教えてもらった内容を元に、本記事では「こだわり」と「儲け」の間で揺れる農業経営のリアルを考察します。
赤字でも米づくりを続ける理由、経営としての農業に必要な視点、そして地域内外とのつながりによる新しい展望まで──。
農業の現場に立って感じた“本音”と“希望”を、できる限り丁寧にお伝えしたいと思います。
本記事のポイント
- 農家のこだわりと収益の両立を考察
- 強みを活かす経営視点と差別化戦略
- 外部との連携が未来の農業をひらく
こだわりと儲けのはざまで揺れる米農家の現実
-150x150.jpg)
「米づくりは“こだわり”か“儲け”か?」──18名の農家さんとの対話を通じて見えてきたのは、想いと現実の狭間で揺れる姿でした。農業を続けるために必要なこととは何か。こだわりと経営の両立を考えます。
(1)米づくりに込める「想い」が農家の支え
多くの農家さんが「良い米を届けたい」という強い想いを胸に、毎年の米づくりに真摯に向き合っています。
たとえ収支が赤字でも、収穫の喜びや、お客様からの「美味しかったよ」という声が心の支えになっていると話されます。
中には、収益が思うように出ない中でも、色彩識別機や低温倉庫といった高額な設備を導入し、品質へのこだわりを貫く方もいます。
その姿勢には、頭が下がる思いです。
(2)利益がなければ続けられない。持続可能な農業経営へ
品質へのこだわりがあるからこそ、効率を重視したくないというお気持ちはよく分かります。
しかし、農薬や肥料の価格が高騰する中で、利益を確保できなければ、家族の暮らしや来年の営農を支えることが難しくなります。
農業は、ただ食べ物を作るだけでなく、地域の文化や景観を守る役割も果たしています。
それだけに、利益の出る仕組みをつくらなければ、いずれ地域の農業そのものが成り立たなくなってしまいます。
だからこそ、経営としての視点が求められているのです。
(3)こだわりを“伝える力”に変える:価値が伝わる価格と顧客関係のつくり方
①素晴らしい生産活動に敬意を
日々の作業に追われながらも、安心・安全で美味しいお米を作り続けておられる農家の皆さんの姿には、本当に頭が下がります。
作業の大変さを考えれば、「一度、米づくりをやってみてから言ってほしい」という農家さんの気持ちにも共感しますし、地域の農業を守るという強い使命感にも敬意を表したいと思います。
②品質と顧客の感覚にズレはないか見直してみる
米の品質について、農家さんの間でも考え方には違いがあります。
ある農家さんは「自分が納得できる最高の品質を目指したい」と、細部にまでこだわりぬいておられました。
一方で、別の農家さんは「米の味なんて大して変わらんよ、わからんもんだ」と率直に話されていました。
もちろん、どちらも「一定以上の品質を担保したうえで」の話であることは間違いありません。
私は後者の感覚の方が、市場の現実に近いように感じます。
つまり、お客様の多くは“70点以上の品質”で十分満足している場合が多く、それ以上の違いを明確に感じ取れる方は多くないのではないでしょうか。
そうであれば、90点から95点を目指すために多額のコストをかけ続けることは、経営の効率性という観点では見直す余地があるかもしれません。
-150x150.jpg)
一方で、「きわめて鋭い味覚を持つ方」や「高くても品質の良い商品を求める方」といった顧客も、もちろん存在します。そうした方々の価値観に応えることも、非常に重要です。ただし本記事では、そうした顧客価値を見極めることなく、やみくもに品質を追い求めることの危険性に焦点を当てています。
これは、かつての日本の製造業と似た構造にも見えます。
高度な技術や高機能を追求するあまり、顧客のニーズとのズレが生まれ、市場ではシンプルで安価な海外製品に負けてしまう…。
同じことが、農業の現場でも起きつつあるのではないでしょうか。
こだわりを否定するわけではありません。
ただ、「誰のために、どの水準を目指すのか」を改めて見つめ直し、顧客の価値観に寄り添った価格設定や関係づくりを考えることが、持続可能な農業経営の鍵になると思います。
農業は「ものづくり」であり「経営」である
-150x150.jpg)
農業は“ものづくり”であり、“経営”でもあります。いいものを作るだけでは立ち行かない時代、必要なのは「誰にどう届けるか」の視点。強みを活かし、数字で見える経営へと変えていく、そのヒントを探ります。
(1)「いいものを作れば売れる」は過去の話
昔は「いいものを作れば自然と売れる」と言われていました。
しかし、現在は情報や選択肢があふれる時代。
品質だけでは差別化が難しくなっています。
だからこそ、「誰に、どんな価値を届けるのか」という視点が不可欠です。
お客様のニーズを起点に物事を考える「マーケットイン」の発想を取り入れることで、農業にも新しい道が開けるはずです。
農業に従事させてもらって、農業と製造業は非常に近しい関係性にあると感じました。
(2)自分たちの強みを見つけ、差別化につなげる
農家ごとに土壌や気候、栽培方法、こだわりの視点は異なります。
それらはすべて「強み」になります。
たとえば、「棚田で育てたお米」「雪解け水で育てた清らかなお米」「30年無農薬でやってきた信頼」といった特徴は、大きな付加価値となります。
これらの強みを改めて認識し、お客様に伝わる形にすることで、他と差別化された存在になれるのです。
強みを活かしたブランドづくりや情報発信は、これからの農業経営における重要な柱です。
(3)感覚に頼らず、数字で見える経営へ
経験と勘も農業には欠かせませんが、それに加えて「数字で見える経営」への移行が必要です。
たとえば、1反ごとに収支を把握できれば、利益の出ていない圃場を見直すことができますし、設備投資の回収計画も立てやすくなります。
経営はいかに計画と実績の差異を小さくする事が肝です。
手間をかけた分だけ、数字で結果が見えるようになると、不安の少ない経営が実現できます。
農家の未来をひらく「外とのつながり」
-150x150.jpg)
農業の未来を支える鍵は「外とのつながり」にあります。専門家や商工会、地域団体との協働が、新たな可能性を生み出します。農業を“志事”として次世代へつなぐために、今できる一歩を考えていきましょう。
(1)専門家や地域支援を「頼れる味方」として考える
農業は一人で全てをこなすには限界があります。
収支の整理、補助金の活用、販路の開拓…。
こうした課題に向き合うためには、税理士や経営コンサルタントなどの専門家の知見を借りることも大切です。
「費用がかかる」「難しそう」と感じるかもしれませんが、それ以上の価値が返ってくることも多いです。
経営改善は、一歩踏み出すところから始まります。
(2)商工会や地域団体との関わりがヒントになる
農業の現場はどうしても閉じた世界になりがちです。
しかし、商工会議所や自治体の支援機関、地域おこし団体などと関わることで、新しい販路や仲間との出会いがあります。
例えば、商工会では農業者向けの経営相談窓口が設けられる動きもあり、地域内での「異業種連携」や「情報交換」が新たなビジネスの種になることもあります。
外とのつながりが、次の展開への大きなヒントになるのです。
(3)農業を“志事”として次世代へつなぐために
「もう農業は儲からない」「子どもには継がせたくない」という声も聞きますが、それは“儲からない仕組み”の中に閉じ込められているからかもしれません
農業が、しっかり生活を支え、誇りを持てる“志事”として認識されるようになれば、次の世代にも希望をつなげるはずです。
そのためには、「こだわりと儲けの両立」が欠かせません。
未来の担い手が「自分もやってみたい」と思える農業へ。私たちが今、環境を整えていくことが求められています。
こだわりと経営力が農業の未来をつくる
農業は、ただ米を作るだけの仕事ではありません。
地域の文化を守り、次世代につなぐ「志事(しごと)」でもあります。
だからこそ、品質へのこだわりと、利益を確保する経営視点の両立が欠かせません。
専門家や地域との連携を通じて、持続可能な農業の形を築くことが、これからの時代に求められる一歩だと強く感じました。