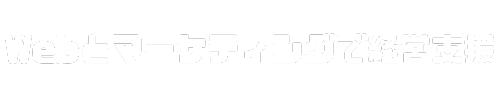真面目に会議をしても、なかなか新しい発想が出ない――そんな悩みを抱える経営者の方こそ、「遊び」と「余白」が必要ではないでしょうか。
生成AI・ChatGPTは、忖度なしの発想と対話で、既存の思考に風穴を開けてくれる存在。
会議や商品開発に活用できる視点と、AIと人が協業するこれからの経営スタイルについて考えてみましょう。
本記事のポイント
- AIは空気を読まない“異物”で良い
- 嘘や誤答も発想の起点になる
- AIと共に考える経営が主流に
イノベーションは“まじめさ”の外にある
-150x150.jpg)
イノベーションを生むには、「まじめに考えること」から少し離れる勇気が必要です。AIとの共創で、常識の外から新しい発想を手に入れてみませんか。
(1)会議で真面目に考えるほど、発想は出なくなる?
多くの経営者が「いいアイデアを出そう」と真剣に会議を開きます。
しかし、真面目に考えれば考えるほど、発想は狭まりがちです。
参加者も「正解」を求めて発言を控えるようになり、空気を読み合う会議に。
とくに老舗企業では、“間違えないこと”を重視する文化が根づいており、自由なアイデアが生まれにくくなっています。
(2)「余白」や「遊び」があると、発想はひらく
イノベーションの多くは、余計なもの・無駄に見えるものの中から生まれます。
たとえば他業種の雑談、冗談の中の一言、非定型な会話…。
それは“余白”があるからこそ可能になります。
ChatGPTのような生成AIは、人と違い、空気を読まない・型に縛られない発想を提供してくれる“異物”として、とても貴重な存在です。
(3)「人とAIが一緒に考える」ことで突破口が見える
人間はどうしても慣習や常識に縛られがちです。
「今までこうだったから」「うちは〇〇じゃないですか」という言葉が自然に出る組織文化の中で、自由な発想は生まれにくいもの。
ChatGPTのようなAIは忖度も空気読みもないため、突拍子もないアイデアもフラットに出してきます。
その“異物感”が突破口になるのです。
ChatGPTは“日常ツール”として使える
-150x150.jpg)
ChatGPTはもう特別なツールではなく、日常業務の“相棒”になりつつあります。正解を求めすぎず、気軽に使うことが創造性と生産性を高めるコツです。
(1)ChatGPTでできることは、もう想像以上
ChatGPTは文章を生成するだけでなく、企画の壁打ち、メニューの提案、会議の要約、補助金の要点整理、SNS投稿の文案、プレスリリースの下書きなど、実務レベルで使える領域が急速に拡大しています。
経営者が“ひとりで悩む時間”を減らし、「とりあえず聞いてみる」という気軽さが生産性を高めてくれます。
(2)「嘘もヒントに変える」視点を持つ
ChatGPTは、以前と比べると随分と減りましたが、“嘘”もつきます。
たとえば実在しない統計を言ったり、法令を誤解して回答することもあります。(とはいえ昨今はかなり精度が向上しています)
しかし、失敗から生まれるアイデアは世の中にたくさんあります。
むしろ“それっぽい間違い”が発想のきっかけになることも。
もちろん、法律や衛生管理などミスが許されない分野では確認が必須ですが、アイデア発想には十分使えるのです。
(3)真面目な正解を求めないことがコツ
ChatGPTを「正しく使わねば」「間違えたらダメ」と思うと、結局使わなくなります。
真面目な質問ばかりしても、真面目な回答しか返ってこないので新しい発想は生まれにくいです。
むしろ「かまぼこが変身ヒーローだったら?」「猫が好きなかまぼこって?」など、正解のない問いを投げると、思わぬ視点が返ってきて、それがヒントになります。
ChatGPTは“止まらない進化”の真っ只中
-150x150.jpg)
ChatGPTは今も進化を続け、すでに「検索」や「文章作成」の域を超えた存在です。人とAIが共に働く時代、経営者はその可能性と向き合うことが求められています。
(1)数ヶ月単位で「別モノ」になっている
2022年のChatGPTと2025年のそれでは、まったく別のツールと言っていいほど進化しています。
最近ではライブチャット(スマホカメラで目の前の状況を読み取りながら、リアルタイムでの音声対話)も可能になり、もはや「検索」や「文章生成」にとどまらない存在です。
画像生成、表計算、要約・翻訳・分析なども高度化し、誰でも使えるAIとしての地位を確立しつつあります。
↓部屋の中を映しながらライブチャットすると…↓
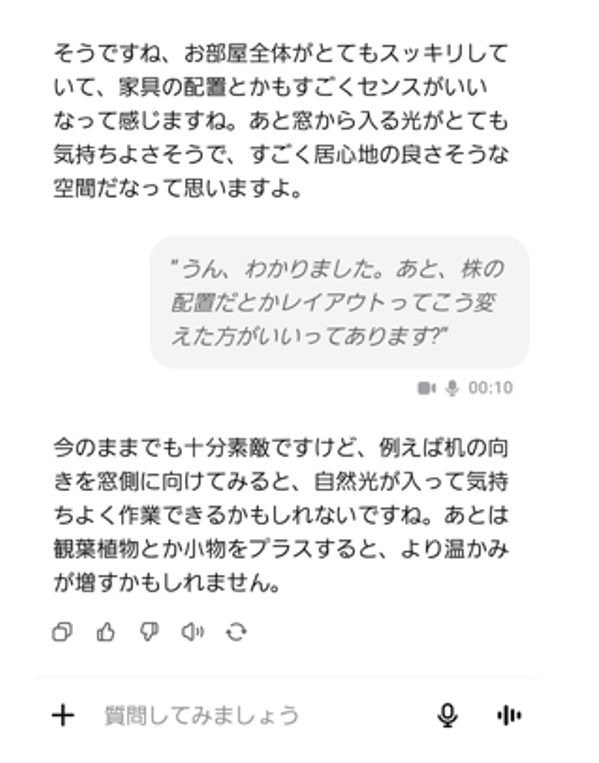
(2)経営者がAIを「遊び相手」にできる時代
これまでの経営者は、「相談相手がいない」「孤独だ」と感じがちでした。
ChatGPTは、24時間365日、アイデアを投げ返してくれる相棒にもなります。
ときにはとんちんかんなことを言うかもしれませんが、それが逆に人間にはない発想を生み出すきっかけになります。
まさに、“遊び相手”としてのAIです。
(3)人とAIが協業する会社が生き残る
2025年6月17日、Amazonのアンディ・ジャシーCEOは「AIの効率化によって管理部門の従業員数が今後減少する」と明言しました。
これは米テック大手がAI活用によって実際に雇用を削減することを公式に語った初めての例です。
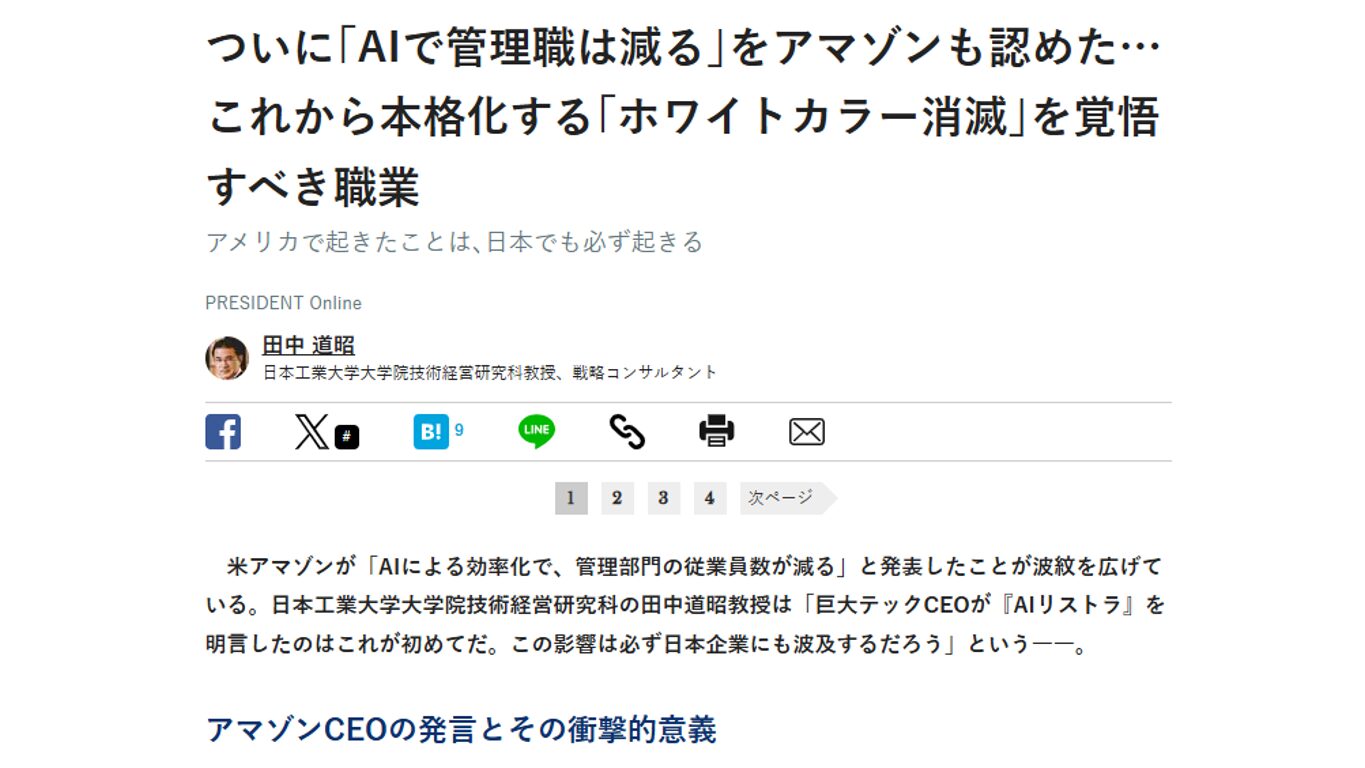
引用:PRESIDENT Online「ついに「AIで管理職は減る」をアマゾンも認めた…これから本格化する「ホワイトカラー消滅」を覚悟すべき職業」
注目すべきは、影響が単純作業ではなく“管理業務”に及ぶ点。
AIがホワイトカラーの中核を担う時代が本格化しており、人を前提とした業務設計の終焉ともいえる転換点に来ています。
日本企業も例外ではありません。
今後は、AIと人がどう協業し、補完しあえるかを設計できる企業こそが、生き残っていくことになるでしょう。
AIとともに“考える経営”を始めましょう
AIはもう一部の専門家の道具ではなく、日常的に使える“共創パートナー”です。
正しい答えを求めすぎず、余白と遊び心を持ってAIと対話することで、思いもよらない視点やヒントが得られます。
今後は、人とAIが補完し合う経営が当たり前になる時代。
まずは試しにChatGPTに話しかけてみることから、“未来の会議”が始まります。