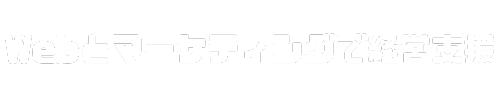地域密着型の和菓子屋を事例企業として、価格設定の本質と観光土産から学べる“価値”のつくり方を考えます。
価格は原価に利益を乗せるだけでは決まりません。
顧客の感情や体験、商品特性に基づく「価格感受性の低さ」を理解することで、地域ブランドを強化しながら収益を高める戦略が可能となります。
本記事のポイント
- 原価主義ではなく価値主義で価格を決める
- 価格感受性を下げる3つの仕組みを理解
- 地域ブランドを高める高価格戦略の意義
価格設定の本質を理解する
-150x150.jpg)
価格設定は単に原価と利益の足し算ではありません。顧客の「価値認識」を反映させることが利益最大化につながる視点です。
(1)中小企業の価格設定が抱える課題
多くの中小企業では「原価に利益を上乗せする」方法で価格を決めています。
一見シンプルで分かりやすいですが、顧客の価値認識を反映していないため、利益を最大化できません。
和菓子業界でも同様に、競合の増加とともに「差別化ができない=価格競争に陥る」というリスクを抱えています。
(2)価格感受性とは何か?
価格感受性とは、顧客が「価格の違いにどの程度敏感に反応するか」を示す概念です。
例えばスーパーで売られる日常食品は1円でも安い方を選ばれやすく、価格感受性が高い(価格が購入の判断に大きく影響)商品です。
一方、旅行先で買う限定の土産物を「安かったから買おう」となるでしょうか。
「高いけどせっかくだから買おう」もしくは「ここでしか買えないんだし、値段なんて気にしない」という方が多いと思われます。
土産物は価格感受性が低い典型例です。
(3)和菓子屋が注目すべき「非日常価値」
とある和菓子店経営者は、地元での認知度を基盤に観光客需要を取り込みたいと考えています。
このとき重要なのが「日常」から「非日常」への価値転換です。
観光客にとって土産物の和菓子は「旅の思い出」「土地の象徴」であり、単なる食べ物以上の体験価値を持ちます。
ここに価格戦略のヒントがあります。
価格感受性を下げる3つの仕組み
-150x150.jpg)
価格感受性を下げる仕組みには「比較困難性」「限定性・希少性」「非日常体験との結びつき」があり、土産物は顕著です。
(1)比較困難性:価格競争からの脱却
土産物の大きな特徴は「比較が難しい」点です。
観光地でしか買えない、地域性を打ち出した和菓子は、同じような商品と直接比べられる機会がほとんどありません。
これにより「安くしないと売れない」という発想から脱却でき、ブランド力を活かした価格設定が可能となります。
(2)限定性・希少性:ここでしか買えない価値
観光客は「今ここで買わなければ手に入らない」という心理に動かされます。
特に限定パッケージや季節限定の和菓子は、希少性によって価格が高くても納得感を持たせられます。
これはまさに「供給制約」が需要を高める典型的なケースであり、地域ブランド化にも直結します。
(3)非日常的体験との結びつき:情緒的価値の上乗せ
価格感受性を下げる最大の要因が「体験との結びつき」です。
旅の記憶や感情とリンクした商品は、単なるモノではなく「思い出の一部」として価値を持ちます。
例えば、上越妙高駅で新幹線を待つ時間に食べた和菓子が「特別な旅行体験」として記憶に残れば、価格そのものは二次的な意味しか持ちません。
地域活性化につなげる価格戦略
-150x150.jpg)
高価格戦略は収益増加にとどまらず、地域ブランドの価値を高めます。強みを価格に反映し、体験価値を活かすことが重要です。
(1)高価格戦略がもたらす地域ブランド効果
価格を適切に高めに設定することで、単なる収益増加だけでなく「地域ブランドの格」を引き上げる効果があります。
「あの地方のお菓子はちょっと高いけど、むちゃくちゃ美味しい」という評判は、地域全体の観光価値を高めることにつながります。
(2)自社の強みを価格に反映させる
自社の強みが「地元での高い認知度」と「県外アンテナショップでの取り扱い」であるとします。
その強みを活かすには「地域の象徴」としてのプレミア感を前面に出し、価格設定に織り込むことが重要です。
たとえば「妙高の雪をイメージした限定和菓子」として、通常より高い価格でも納得されやすい構造をつくれます。
(3)身近な実体験から:同じ米でも価格が違う理由
私の体験として、上越妙高駅で販売されている地元産のお米は、同じ銘柄でもスーパーより高い価格で売られています。
3号や6合など比較的小さいサイズの取り扱いが多いですが、容量のみで考えれば割高です。
これは「この駅でしか買えない限定感」と「旅行の非日常体験」が価格に上乗せされていると考えられます。
この事例は「価格感受性が下がる理論」が実生活で正しいことを証明しています。
価格設定は「価値」を基準に考える
価格は単なる原価と利益の積み上げでは決まりません。
観光土産に見られるように「比較困難性」「限定性」「非日常体験」といった要素が、顧客の価格感受性を下げ、価値を高めます。
地域密着型の和菓子屋が高価格戦略をとることで、利益を確保しつつ地域ブランドを強化する道が開かれるのです。