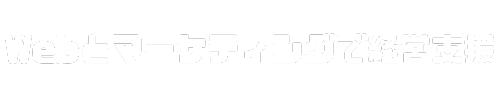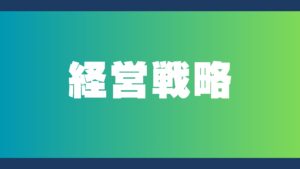情報があふれる現代、経営者にとって「意思決定」は年々難しさを増しています。
AIやネット、書籍など多様な情報源に囲まれながらも、「決められない」「相談できない」と感じることは自然なこと。
この記事では、情報過多の時代において、迷いの中でも一歩を踏み出すための「直感×論理」の意思決定法を、3つの視点からお伝えします。
本記事のポイント
- 一人で抱えず、相談できる関係を持つ
- 情報源は分散し、視野を広く持つ
- 直感で動き、論理で整える習慣を
なぜ、意思決定が難しくなっているのか?:情報があふれる時代の経営
-150x150.jpg)
かつてないほど情報があふれる現代、特に経営者にとって「決めること」は簡単ではありません。一人で抱える重圧、選択肢の多さ、相談相手の不在——。そんな経営判断の迷いに向き合い、少しでも前に進むための考え方を、3つの視点から整理します。
(1)経営判断を「一人で抱える」現実
資材の製造から販売、経理、経営戦略までを一人で担う経営者にとって、日々の意思決定は想像以上に重たいものです。
「誰にも相談できない」「本当にこれで良いのか」と不安を抱えながら、それでも事業を止めるわけにはいかない——そんな毎日を送っておられる方も多いのではないでしょうか。
また特に先代から事業を引き継いでいる場合、成果を残したいという思いと、失敗を避けたいという慎重さが交錯し、つい判断を先送りしてしまうこともあるかもしれません。
これは決して意志が弱いのではなく、「誠実で責任感がある方ほど陥りやすい葛藤」と言えるのではないでしょうか。
(2)選択肢が多すぎると、むしろ「決められない」
近年、インターネットやAIの普及により、私たちは膨大な情報にアクセスできるようになりました。
経営に役立つノウハウや成功事例、専門家の意見など、検索すれば無数に出てきます。
一見、心強いように思えますが、実際には「情報が多すぎて何が正しいのかわからない」「結局、何も選べずに終わる」と感じる方も少なくありません。
この現象は心理学の世界では「ジャム理論(選択の逆説)」としても知られています。
ある実験では、24種類のジャムを並べた売り場と、6種類だけを並べた売り場を比較したところ、多くの人が立ち寄ったのは24種類の売り場でした。
しかし、実際に購入したのは6種類だけの売り場の方がはるかに多かったのです。
これは、選択肢が多すぎると、人は最適解を見つけるプレッシャーや情報処理をし切れず、決められなくなるという傾向を示しています。
経営判断においてもこれは同じです。
ネットや書籍、SNS、AIなど、あらゆる媒体から得た多様な情報が、かえって判断を迷わせ、行動に移ることを妨げているのかもしれません。
(3)「決めきれない」のはごく自然なこと
意思決定に迷いが生じることは、人として、そして経営者としてごく自然なことです。
特に、事業の未来がかかる判断を前に、慎重になるのは当然の反応です。
ですが、それを「優柔不断だ」「自分は経営者に向いていないのでは」と責める必要はまったく無いかと思います。
大切なのは、“決める力”そのものではなく、「どのように決めるか」という“意思決定のプロセス”を持っているかどうかです。
そのためのヒントとなるのが、次章でお伝えする「相談」「情報分散」、そして「直感と論理のバランス」といった視点です。
一人で抱え込まない:情報の扱い方と相談の価値
-150x150.jpg)
経営判断に迷ったとき、すべてを一人で抱え込む必要はありません。AIやネットも参考になりますが、最も頼りになるのはやはり「人の声」。多様な視点と対話を通じて、情報を整理し、納得できる意思決定へつなげていく方法を探ります。
(1)AIも便利だが、やはり「人の声」に勝るものはない
近年はChatGPTのようなAIツールも登場し、気軽にアイデアを出せる時代になりました。
経営相談の入り口として活用するのも一つの手だと思います。
ただ、AIは基本的にあくまで「ネット上の膨大なデータ」に基づいて回答しているため、あなた自身の「地域」「顧客」「タイミング」に完全にフィットするわけではありません。
その点、地域の商工会議所や異業種交流会など、リアルな「人と人」のつながりには、今この瞬間の現場感覚があります。
どれほど小さな気づきであっても、人との会話の中で得られるヒントは、AIではカバーできない“空気感”や“タイミング”を含んでいます。
(2)情報源は意図的に「分散」させる
一つの考え方や成功事例に固執してしまうと、他の選択肢を見失ってしまう危険があります。
特定の書籍、著名人の発信、AIの助言など、いずれも有益ではありますが、どれか一つに頼りすぎると視野が狭くなってしまいます。
経営においては「複眼的な視点」が非常に重要です。
複数の情報源を持ち、「誰のどの意見が自分の状況に一番近いか」「この人は何を前提に話しているのか」といった問いを持つことが、冷静な判断につながります。
その意味でも、「他業種の経営者」「顧客の声」「社外の専門家」といった“異なる立場の視点”を取り入れることが、情報に振り回されないための知恵になります。
(3)「相談」は決して弱さではない
ご自身の判断に責任を持ってきたからこそ、「相談すること=弱さ」だと感じてしまう方もいらっしゃいます。しかし、本当にそうでしょうか?
相談とは、「他者の視点を借りることで、自分の視野を広げる行為」です。
最終的に決めるのは自分ですが、そこに至るまでの道のりに、“壁打ち”の相手がいるかどうかで、判断の質は大きく変わってきます。
たとえば、マーケティングに詳しい外部の専門家にヒントを求める。
あるいは、同じ悩みを抱える異業種の仲間と本音で話す。
そうした行為は、けっして甘えではなく、むしろリーダーとしての「柔軟性」の現れではないでしょうか。
「直感×論理」で決める:小さな一歩のための意思決定法
-150x150.jpg)
正解を探し続けるより、「納得できる決断」を積み重ねていくことが、経営を前に進める鍵になります。ここでは、小さな一歩を踏み出すために有効な「直感」と「論理」の活かし方について、具体的な順序と考え方を整理していきます。
(1)まず「直感」で方向性をつかむ
「この商品、なんとなく売れそうだな」「あの市場、伸びている気がする」——こうした直感は、決して根拠のない思いつきではありません。
実はこの“なんとなく”には、あなたがこれまで現場で培ってきた知識、経験、観察力が詰まっています。
だからこそ、まずはその直感を一度、信じてみることが大切です。
特に不確実性の高い現在では変化への対応が早く求められる環境では、「理屈をすべて詰めてから動く」よりも、「方向性だけ見定めてまず一歩踏み出す」方が、結果として大きな成果につながるケースが多いのです。
もちろん、いきなり大きな賭けに出る必要はありません。
たとえば、「新商品を出す」と決めたら、まずは小規模なテスト販売から始めるなど、リスクを最小限にした形で直感を活かす工夫が可能です。
(2)直感を「論理」で補正していく
直感を起点にしても、それを検証するための「論理」は必要不可欠です。
「この新しい販路は良さそう」と感じたら、その販路の市場規模はどうか、既存顧客との重なりはあるか、利益率は維持できるかなど、数字や事例で確かめていく作業が次に来ます。
この“直感→論理”の順番は、実際の経営では非常に理にかなっています。
直感で動いた方が、スピード感があり、行動にも意志が乗ります。
そのうえで、論理で確認することで、外部への説明も可能となり、従業員や取引先の理解も得られやすくなります。
また、仮に最初の直感が完全に正しくなかったとしても、論理的に微調整することで、現実的なプランに落とし込むことができます。
この“修正力”こそが、持続可能な意思決定を生む力です。
(3)「論理→直感」の順番がうまくいかない理由
逆に、情報を集めすぎてから「直感に従って選ぶ」という方法は、うまくいかないことが多いと感じています。
なぜなら、情報は集めれば集めるほど「完璧な正解」を求めてしまい、判断のハードルがどんどん上がってしまうからです。
そして最終的には、「もっと調べてからにしよう」「もう少し様子を見よう」と、行動自体が先延ばしになってしまいがちです。
これは先ほどのジャム理論にも通じる話ですが、「最適解」を探し続けるより、「納得解」で一歩踏み出すほうが、結果的にビジネスを前に進めやすくなります。
迷う時代の「納得できる決断力」とは
「正しい答えを出すこと」よりも、「自分が納得できる選択を積み重ねること」が、経営の前進につながります。
一人で抱え込まず、他者の視点に耳を傾けながら、まずは直感で方向を定めてみてください。
その直感を、論理の力で微調整していくことが、結果的に強く柔軟な意思決定力を育てていきます。
決められないのは弱さではなく、誠実さの証。
だからこそ、自分なりの「決め方」を持つことが大切なのです。